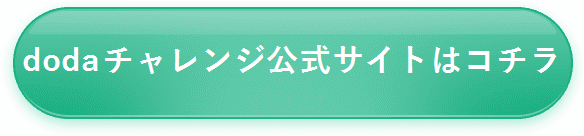dodaチャレンジで断られた!?断られる人の特徴や断られた理由について解説します

dodaチャレンジは、障がい者雇用に特化した転職エージェントとして、多くの求職者をサポートしています。
しかし、中には「dodaチャレンジに登録したけれど、求人を紹介してもらえなかった」「サポートを断られてしまった」という声もあります。
なぜこのようなことが起こるのでしょうか? その理由には、求職者の希望条件やdodaチャレンジのサポート範囲など、いくつかの要因が関係しています。
ここでは、dodaチャレンジで求人を紹介してもらえない理由や、サポートを断られるケースについて詳しく解説します。
断られる理由1・紹介できる求人が見つからない
dodaチャレンジに登録しても、希望条件とマッチする求人がない場合、求人の紹介が難しくなることがあります。
特に、以下のような条件を設定していると、求人の選択肢が狭まり、結果的に紹介できる求人がなくなる可能性があります。
希望条件が厳しすぎる(在宅勤務限定、フルフレックス、年収500万円以上など)
最近では、在宅勤務やフルフレックスの求人も増えてきていますが、それでも障がい者雇用枠での求人は「出社が基本」となる企業が多いのが現状です。
また、年収500万円以上などの高収入求人を希望する場合は、即戦力となるスキルや経験が求められるため、該当する求人が少なくなります。
そのため、希望条件を厳しく設定しすぎると、マッチする求人が見つからず、dodaチャレンジ側でも紹介が難しくなってしまうことがあります。
希望職種や業種が限られすぎている(クリエイティブ系、アート系など専門職など)
「デザイナー」「イラストレーター」「アニメーター」「映像編集」などのクリエイティブ系やアート系の仕事は、一般的な事務職や営業職に比べると求人数が少ないため、紹介できる求人が見つからないことがあります。
また、専門職の場合、実務経験やポートフォリオの提出が求められることが多く、企業側も即戦力を重視する傾向があります。
そのため、未経験者がこの分野を希望する場合、選択肢が非常に限られてしまうのが現実です。
勤務地が限定的(地方で求人自体が少ない)
地方に住んでいる場合、そもそも障がい者雇用枠の求人が少ないケースがあります。
特に、人口が少ない地域では、企業の数自体が少ないため、希望条件に合う求人が見つかりにくくなります。
また、大企業の多くは東京や大阪などの都市部に集中しているため、地方で希望する職種の求人を探すのが難しいこともあります。
こうした場合は、在宅勤務の選択肢を広げるか、通勤可能な範囲を少し広げることで、マッチングの可能性を高めることができます。
断られる理由2・サポート対象外と判断される場合
dodaチャレンジでは、一定の条件を満たしている求職者を対象にサポートを提供しています。
そのため、以下のような場合は、登録はできても求人の紹介が難しくなることがあります。
障がい者手帳を持っていない場合(「障がい者雇用枠」での求人紹介は、原則手帳が必要)
dodaチャレンジは、障がい者雇用枠の求人を紹介するサービスのため、基本的には障がい者手帳を持っていることが前提となります。
ただし、一部の企業では、医師の診断書や通院履歴があれば応募できるケースもあります。
障がい者手帳を持っていなくても、就職を希望する場合は、一度キャリアアドバイザーに相談してみるのがおすすめです。
長期間のブランクがあって、職務経験がほとんどない場合
長期間のブランクがあると、「職務経験が少ない」「職場復帰が難しいのでは?」と企業側が判断し、応募できる求人が限られることがあります。
また、過去の職歴が少ない場合や、実務経験がほとんどない場合も、即戦力を求める企業とのマッチングが難しくなることがあります。
このようなケースでは、職業訓練を受けたり、アルバイトやパートなどで経験を積んでから正社員の求人に応募するという方法も考えられます。
dodaチャレンジで求人を紹介してもらえなかった場合、必ずしも求職者のスキルや経験が不足しているというわけではなく、希望条件やdodaチャレンジ側の求人状況によることが多いです。
もし「求人を紹介してもらえなかった」と感じた場合は、キャリアアドバイザーと相談しながら希望条件を調整したり、他の転職エージェントと併用してより多くの選択肢を探すことをおすすめします。
状態が不安定で、就労が難しいと判断される場合(まずは就労移行支援を案内されることがある)
dodaチャレンジでは、求職者の状況に応じて最適な就職支援を行っています。
しかし、健康状態が不安定で、現時点で安定して働くことが難しいと判断される場合、すぐに求人を紹介できないことがあります。
特に、最近の通院履歴や医師の診断によって「まだフルタイムで働くのは難しい」「もう少しリハビリが必要」と判断された場合、まずは就労移行支援や短時間勤務が可能な環境を整えることを勧められることがあります。
就労移行支援では、働くためのスキルや職場環境への適応を学ぶことができ、将来的に正社員としての就職を目指すための準備ができます。
もし現在の状態で働くことに不安がある場合は、キャリアアドバイザーに相談しながら、自分に合ったステップを考えることが大切です。
断られる理由3・面談での印象・準備不足が影響する場合
dodaチャレンジの面談では、キャリアアドバイザーが求職者の適性や希望条件を詳しくヒアリングし、最適な求人を紹介する流れになっています。
しかし、面談の準備が不足していると、希望に合った求人を見つけるのが難しくなることがあります。
障がい内容や配慮事項が説明できない
面談では、企業が配慮できる範囲を明確にするために、障がいの特性や必要な配慮事項について質問されることが多いです。
「どんな配慮があれば働きやすいか」「どのような業務なら無理なくこなせるか」を具体的に伝えられないと、キャリアアドバイザーも求人を探しにくくなってしまいます。
そのため、事前に自分の働き方や必要な配慮について整理しておくことが重要です。
どんな仕事をしたいか、ビジョンが曖昧
「どのような仕事をしたいのか」が明確でないと、キャリアアドバイザーも適切な求人を提案するのが難しくなります。
「とにかく働きたい」「どんな仕事でもいい」と考えている場合でも、ある程度の方向性を決めておくことが大切です。
例えば、「事務職に興味がある」「人と関わる仕事がしたい」など、大まかな希望でも構いません。
自分の得意なことや興味のある分野を考え、面談でしっかり伝えられるように準備しておくと、よりスムーズに求人を紹介してもらいやすくなります。
職務経歴がうまく伝わらない
面談では、これまでの職歴やスキルについて詳しく話す機会がありますが、職務経歴を整理できていないと、アドバイザーに適切な情報が伝わらず、求人のマッチングが難しくなることがあります。
過去の職歴が複数ある場合は、それぞれの仕事内容や担当業務、実績などを簡潔にまとめておくと、スムーズに伝えられます。
また、ブランクがある場合は、その期間に行っていたこと(資格取得やリハビリなど)についても準備しておくとよいでしょう。
断られる理由4・地方エリアやリモート希望で求人が少ない
dodaチャレンジは全国対応の転職サービスですが、エリアによって求人数に偏りがあり、地方在住者やリモートワーク希望者は紹介可能な求人が少なくなることがあります。
地方在住(特に北海道・東北・四国・九州など)
障がい者雇用の求人は、東京・大阪・名古屋といった都市部に集中する傾向があります。
そのため、北海道・東北・四国・九州などの地方エリアでは、そもそもの求人件数が少なく、希望する条件に合う仕事が見つかりにくいことがあります。
地方での就職を希望する場合は、地元の障がい者雇用に特化した転職サービスやハローワークと併用することで、より多くの選択肢を確保することができます。
完全在宅勤務のみを希望している場合(dodaチャレンジは全国対応ではあるが地方によっては求人がかなり限定される)
近年、在宅勤務の求人は増えていますが、完全在宅勤務を希望すると、選択肢がかなり限定されてしまいます。
特に、障がい者雇用枠では「出社とリモートの併用」が求められるケースが多く、フルリモートの求人は少なめです。
また、リモートワークを導入している企業でも、「一定期間は出社が必要」「本社の近くに住んでいることが条件」などの制約がある場合があります。
そのため、完全在宅勤務にこだわりすぎると、紹介可能な求人が限られてしまいます。
もしフルリモートでの就職を希望する場合は、在宅勤務に強い転職サービスを併用したり、業務委託やフリーランスの仕事も視野に入れるなど、幅広い選択肢を考えることが大切です。
断られる理由5・登録情報に不備・虚偽がある場合
dodaチャレンジに登録する際、求職者が入力する情報は、求人を紹介するうえで非常に重要な判断材料になります。
そのため、登録情報に不備があったり、意図的に虚偽の情報を記載してしまうと、求人紹介を受けられなくなる可能性があります。
手帳未取得なのに「取得済み」と記載してしまった
障がい者雇用枠の求人は、基本的に「障がい者手帳を持っていること」が応募条件になっています。
そのため、まだ手帳を取得していない状態で「取得済み」と登録してしまうと、面談時や応募時にトラブルになる可能性があります。
dodaチャレンジでは、企業に応募する際に障がい者手帳の確認を求められることが多いため、実際に手帳を取得していない場合は、正直に申告し、手続きの進捗状況を伝えることが大切です。
手帳の取得予定がある場合は、その旨をキャリアアドバイザーに相談すれば、適切なアドバイスを受けることができます。
働ける状況ではないのに、無理に登録してしまった
求職者の中には、「とりあえず登録しておけば、いつでも就職できるだろう」と考えている人もいます。
しかし、dodaチャレンジでは、すぐに就職する意欲がある人を対象としているため、「まだ働ける状態ではない」と判断されると、求人の紹介が難しくなることがあります。
例えば、治療中で就労が厳しい場合や、働く意思はあるものの具体的な就職準備が整っていない場合は、キャリアアドバイザーとの面談で「就労可能な時期を明確にしてから再度登録すること」を勧められることがあります。
職歴や経歴に偽りがある場合
転職活動を有利に進めようと、職歴や資格について誇張した情報を記載してしまう人もいます。
しかし、dodaチャレンジでは、企業に応募する際に詳細な職務経歴やスキルを確認するため、虚偽の情報はすぐに判明してしまいます。
万が一、経歴詐称が発覚した場合、紹介可能な求人がなくなるだけでなく、今後の転職活動にも悪影響を及ぼす可能性があるため、正しい情報を記載することが大切です。
断られる理由6・企業側から断られるケースも「dodaチャレンジで断られた」と感じる
dodaチャレンジで求人を紹介してもらえたものの、応募後に企業側から不採用となるケースもあります。
このような場合、「dodaチャレンジに断られた」と感じることがありますが、実際には企業の選考基準によるものであり、必ずしもdodaチャレンジ自体が原因ではありません。
不採用は企業の選考基準によるもの
企業の採用基準はそれぞれ異なり、以下のような理由で不採用になることがあります。
– 経験・スキルが企業の求めるレベルに達していない
– 他の応募者との比較で選考が進まなかった
– 企業の社風や職場環境とのマッチングが難しいと判断された
特に、大手企業の障がい者雇用枠では競争率が高く、書類選考の段階で不採用になるケースも少なくありません。
不採用が続くと不安になるかもしれませんが、求人の選択肢を広げる・面接対策を強化するなどの対策を取ることで、次のチャンスに備えることができます。
また、不採用になった場合は、キャリアアドバイザーにフィードバックをもらうことで、改善点を見つけることができます。
面接での受け答えや職務経歴書の内容を見直し、次回の選考に活かすことが大切です。
dodaチャレンジで断られた人の体験談/どうして断られたのか体験談や口コミを調査しました
dodaチャレンジは、障がい者雇用に特化した転職エージェントですが、すべての求職者に求人を紹介できるわけではありません。
実際に登録したものの、希望する求人を紹介してもらえなかったり、サポートを断られてしまった人もいます。
では、どのようなケースでdodaチャレンジから求人紹介を断られてしまうのでしょうか? ここでは、実際の体験談をもとに、その理由を詳しく見ていきます。
体験談1・障がい者手帳は持っていましたが、これまでの職歴は軽作業の派遣だけ。PCスキルもタイピング程度しかなく、特に資格もありません。紹介できる求人がないと言われてしまいました
障がい者雇用枠の求人には、事務職やIT系の仕事が多く含まれており、基本的なPCスキル(Excel・Wordの使用経験など)が求められることが多いです。
そのため、PCスキルがほとんどない場合や、特定のスキル・資格を持っていない場合、紹介可能な求人が少なくなってしまうことがあります。
この場合は、職業訓練や資格取得を検討し、スキルを身につけてから再度転職活動を進めるのがおすすめです。
体験談2・継続就労できる状態が確認できないため、まずは就労移行支援などで安定した就労訓練を』と言われてしまいました。
dodaチャレンジでは、長く安定して働けることを前提として求人を紹介しています。
そのため、体調が不安定で、就労を継続できるかどうか不確実な場合、すぐに転職活動を進めるのではなく、就労移行支援などで職業訓練を受けることを推奨されることがあります。
まずは、無理のない範囲で働くリズムを作り、職場環境に慣れることを優先すると、将来的により良い転職がしやすくなります。
体験談3・精神疾患で長期療養していたため、10年以上のブランクがありました。dodaチャレンジに相談したものの、『ブランクが長く、就労経験が直近にないため、まずは体調安定と職業訓練を優先しましょう』と提案されました
ブランクが長い場合、企業側が「職場復帰できるのか?」「業務に適応できるのか?」といった懸念を持つため、求職者としてのハードルが上がることがあります。
このような場合は、まず短時間のアルバイトや、職業訓練を通じて仕事の感覚を取り戻すことが大切です。
また、キャリアアドバイザーと相談しながら、無理のない範囲で働ける求人を探していくのも一つの方法です。
体験談4・四国の田舎町に住んでいて、製造や軽作業ではなく、在宅でのライターやデザインの仕事を希望していました。dodaチャレンジからは『ご希望に沿う求人はご紹介できません』といわれました
dodaチャレンジは全国対応ですが、エリアによっては求人数に偏りがあります。
特に地方では、大手企業やオフィス勤務の求人が少なく、選択肢が限られることがあります。
また、在宅勤務の求人は増えていますが、特にライターやデザインなどの専門職はフリーランス案件が多く、dodaチャレンジの紹介求人には少ない傾向があります。
このような場合は、在宅ワーク専門の求人サイトやクラウドソーシングサービスを利用するのも一つの方法です。
体験談5・これまでアルバイトや短期派遣での経験ばかりで、正社員経験はゼロ。dodaチャレンジに登録したら、『現時点では正社員求人の紹介は難しいです』と言われました
dodaチャレンジでは、企業とのマッチングを重視しているため、正社員経験がまったくない場合、正社員求人の紹介が難しいことがあります。
このような場合は、まず契約社員や紹介予定派遣などを利用し、段階的に正社員を目指す方法を検討するとよいでしょう。
また、職務経歴書の書き方を工夫し、過去のアルバイト経験でもスキルをアピールできるようにすることが大切です。
体験談6・子育て中なので、完全在宅で週3勤務、時短勤務、かつ事務職で年収300万円以上という条件を出しました。『ご希望条件のすべてを満たす求人は現状ご紹介が難しいです』と言われ、紹介を断られました
在宅勤務や時短勤務の求人は増えてきていますが、すべての条件を満たす求人は限られています。
特に、週3勤務・時短・高収入の条件がそろう求人はほとんどないため、紹介が難しくなることがあります。
この場合は、条件の一部を見直したり、パートや業務委託などの働き方を検討するのも選択肢のひとつです。
柔軟な働き方を取り入れることで、希望に近い仕事が見つかる可能性が高くなります。
体験談7・精神障がい(うつ病)の診断を受けていますが、障がい者手帳はまだ取得していませんでした。dodaチャレンジに登録を試みたところ、『障がい者手帳がない場合は求人紹介が難しい』と言われました
dodaチャレンジは、障がい者雇用枠の求人を紹介するサービスのため、基本的に障がい者手帳を持っていることが応募条件になります。
ただし、企業によっては、医師の診断書や通院履歴があれば応募できるケースもあります。
障がい者手帳をまだ取得していない場合は、まずは取得の手続きを進めるか、手帳がなくても応募可能な求人を扱っている転職エージェントを利用するのがおすすめです。
体験談8・長年、軽作業をしてきたけど、体調を考えて在宅のITエンジニア職に挑戦したいと思い、dodaチャレンジに相談しました。『未経験からエンジニア職はご紹介が難しいです』と言われ、求人は紹介されませんでした
ITエンジニア職は未経験からの転職が可能な職種もありますが、障がい者雇用枠では即戦力を求める企業が多いため、実務経験なしでは求人を紹介してもらえないことが多いです。
特に、在宅勤務のエンジニア職は、高度なスキルが求められる傾向があり、企業側も経験者を優先する傾向にあります。
この場合、まずはプログラミングスクールや職業訓練を活用し、基礎スキルを身につけることが重要です。
Web開発やアプリ開発のポートフォリオを作成し、実務に近い経験を積むことで、未経験からでもエンジニア職に挑戦しやすくなります。
体験談9・身体障がいで通勤も困難な状況で、週5フルタイムは無理。短時間の在宅勤務を希望しましたが、『現在ご紹介できる求人がありません』と断られました
近年、リモートワークの普及により在宅勤務の求人は増えていますが、障がい者雇用枠ではまだフルリモート勤務の求人は限られており、短時間勤務の求人も少ないのが現実です。
特に、完全在宅かつ短時間勤務という条件をすべて満たす求人は非常に少ないため、紹介が難しくなることがあります。
この場合、週数回の出社が可能な求人も視野に入れる、またはフリーランスや業務委託の仕事を検討するといった柔軟な選択肢を考えることが必要です。
また、リモートワーク専門の転職エージェントを活用することで、より多くの求人に出会える可能性があります。
体験談10・前職は中堅企業の一般職だったけど、今回は障がい者雇用で管理職や年収600万以上を希望しました。dodaチャレンジでは『ご紹介可能な求人は現在ありません』と言われました
障がい者雇用枠では、管理職ポジションの求人が非常に少なく、企業の採用基準も厳しいため、年収600万円以上の求人を見つけるのは難しいのが現状です。
このような場合、まずはリーダー職やマネージャー候補など、管理職に近いポジションを目指し、実務経験を積みながらキャリアアップを狙う方法が有効です。
また、ハイクラス向けの転職サービスを利用することで、より高年収の求人に出会える可能性があります。
dodaチャレンジで断られたときの詳しい対処法について紹介します
dodaチャレンジで求人を紹介してもらえなかった場合でも、スキルアップや他の転職支援を活用することで、新たな選択肢を見つけることが可能です。
ここでは、求人紹介を断られた理由ごとに、具体的な対処法を紹介します。
スキル不足・職歴不足で断られたとき(職歴が浅い、軽作業や短期バイトの経験しかない、PCスキルに自信がないなど)の対処法について
スキル不足や職歴の浅さが原因で求人紹介を断られた場合、スキルアップや職務経験を積むことが重要になります。
ハローワークの職業訓練を利用する/ 無料または低額でPCスキル(Word・Excel・データ入力など)が学べる
ハローワークでは、求職者向けの職業訓練を無料または低額で受けることができます。
特に、事務職を希望する場合は、WordやExcelなどの基本的なPCスキルを習得することで、応募できる求人の幅が広がります。
就労移行支援を活用する/実践的なビジネススキル、ビジネスマナー、メンタルサポートも受けられる
就労移行支援では、職場での実践的な業務スキルやビジネスマナーを学びながら、職場適応能力を高めることができます。
障がいに対する配慮を受けながら、働くための準備を整えられるため、職歴が浅い人やブランクがある人にもおすすめです。
資格を取る/MOS(Microsoft Office Specialist)や日商簿記3級があると、求人紹介の幅が広がる
資格を取得することで、スキルを客観的に証明でき、企業側も採用しやすくなります。
特に、事務職を希望する場合は、MOS(Microsoft Office Specialist)や日商簿記3級を取得することで、応募できる求人が増える可能性があります。
ブランクが長すぎてサポート対象外になったとき(働くことへの不安が強い、数年以上の離職や療養期間があるなど)の対処法について
ブランクが長いと、企業側が「職場復帰できるのか?」と懸念を抱きやすいため、まずは短時間勤務や段階的な復職を目指すことが有効です。
– 短時間のアルバイトやパートから始める
– 就労移行支援で職業訓練を受ける
– リワークプログラムを活用して、働くリズムを取り戻す
また、ブランク期間中に取り組んだこと(資格取得、ボランティア活動など)を履歴書に記載することで、企業に対して前向きな姿勢をアピールすることができます。
就労移行支援を利用して就労訓練をする/毎日通所することで生活リズムを整え、安定した就労実績を作れる
ブランクが長い場合や、いきなりフルタイム勤務に不安がある場合は、就労移行支援を利用するのがおすすめです。
就労移行支援では、ビジネスマナーやPCスキルのトレーニングが受けられるだけでなく、毎日決まった時間に通所することで、生活リズムを整えることができます。
また、企業実習や職場体験を通じて、自分に合った働き方を見つける機会もあります。
一定期間の通所実績があると、転職活動の際に「継続して働く意欲がある」と評価されやすくなります。
短時間のバイトや在宅ワークで「実績」を作る/週1〜2の短時間勤務から始めて、「継続勤務できる」証明をつくる
フルタイム勤務が難しい場合は、短時間のアルバイトや在宅ワークから始めて、働くペースを整えるのも有効です。
週1〜2回の勤務からスタートし、徐々に勤務時間を増やしていくことで、継続して働ける証明になります。
また、データ入力やライティングなどの在宅ワークを通じて、仕事の実績を作ることもできます。
これにより、転職活動の際に「ブランク期間中も働く意欲があった」とアピールしやすくなります。
実習やトライアル雇用に参加する/企業実習での実績を積むと、再登録時にアピール材料になる
実習やトライアル雇用を利用することで、実際の職場環境を経験しながら、仕事の適性を確認できます。
企業側も、実習を通じて求職者のスキルや適性を評価できるため、実習後にそのまま採用されるケースもあります。
特に、障がい者雇用枠では、実際に働いてみないと向き不向きが分からないことも多いため、こうした制度を活用することで、転職活動を有利に進めることができます。
地方在住で求人紹介がなかったとき(通勤できる距離に求人が少ない、フルリモート勤務を希望しているなど)の対処法について
地方に住んでいる場合、都市部に比べて障がい者雇用の求人が少ないため、希望する仕事を見つけるのが難しいことがあります。
そんなときは、在宅勤務可能な求人を探したり、地元の支援機関を活用するのがおすすめです。
在宅勤務OKの求人を探す/他の障がい者専門エージェント(atGP在宅ワーク、サーナ、ミラトレ)を併用
dodaチャレンジで在宅勤務の求人が見つからなかった場合は、在宅ワークに特化した障がい者専門エージェントを活用するのも一つの方法です。
atGP在宅ワークやサーナ、ミラトレなどは、在宅勤務可能な求人を多数扱っており、フルリモートや短時間勤務の仕事を探しやすくなります。
複数のエージェントに登録することで、より多くの選択肢を確保できます。
クラウドソーシングで実績を作る/ランサーズ、クラウドワークスなどでライティングやデータ入力の仕事を開始
在宅ワークを希望する場合、クラウドソーシングを活用して、実績を作るのも有効です。
ランサーズやクラウドワークスなどのサイトでは、ライティングやデータ入力の仕事を受注でき、働くスキルを磨きながら収入を得ることができます。
これらの実績を履歴書や職務経歴書に記載することで、企業に対して「在宅での仕事経験がある」とアピールすることができ、採用される可能性が高まります。
地域の障がい者就労支援センターやハローワークに相談する/地元密着型の求人情報が得られる場合がある
地方に住んでいる場合は、地元の障がい者就労支援センターやハローワークを活用することで、地域に密着した求人情報を得られることがあります。
特に、ハローワークには企業の採用担当者と直接相談できる窓口があり、地域にある未公開求人を紹介してもらえることもあります。
都市部にはない地元企業の求人が見つかることもあるため、一度相談してみるのもおすすめです。
希望条件が厳しすぎて紹介を断られたとき(完全在宅・週3勤務・年収◯万円など、条件が多いなど)の対処法について
希望する条件が多すぎると、それに合致する求人が見つかりにくくなることがあります。
特に、完全在宅勤務や週3勤務、高年収などの条件をすべて満たす求人は限られているため、条件を少し緩和することも検討する必要があります。
例えば、
・フルリモートにこだわらず、週1〜2回の出社が可能な求人も探してみる
・勤務日数を調整し、週4〜5日の短時間勤務を検討する
・初めは希望年収より低めの求人でも、キャリアアップの可能性がある企業を選ぶ
といった方法を考えることで、選択肢を広げることができます。
また、企業との面接時に「最初は週3勤務でスタートし、慣れたら週4〜5日に増やしたい」といった柔軟な姿勢を見せることで、採用される可能性が高まることもあります。
を断られたとき(完全在宅・週3勤務・年収◯万円など、条件が多いなど)の対処法について
条件に優先順位をつける/「絶対譲れない条件」と「できれば希望」を切り分ける
転職活動を進めるうえで、自分の希望条件を整理することはとても大切です。
しかし、すべての希望を満たす求人を見つけるのは難しいため、「絶対に譲れない条件」と「できれば希望する条件」を切り分けることが重要になります。
例えば、「完全在宅勤務」「週3勤務」「年収○万円以上」などの希望がある場合、それが本当に譲れない条件なのかを考えてみるとよいでしょう。
もし、完全在宅が難しい場合でも、「週1〜2回の出社なら可能」とすることで、紹介してもらえる求人が増えるかもしれません。
希望条件を柔軟に整理することで、自分に合った求人を見つけやすくなります。
譲歩できる条件はアドバイザーに再提示する/ 勤務時間、出社頻度、勤務地を柔軟に見直す
希望条件を明確にしたら、譲歩できる部分をアドバイザーに再提示し、求人の幅を広げる工夫をしましょう。
例えば、勤務時間や出社頻度、勤務地などを柔軟に見直すことで、紹介可能な求人が増える可能性があります。
完全在宅勤務にこだわらず、リモートワークと出社の併用を検討すると、より多くの企業の選考対象になります。
また、勤務地の範囲を広げて通勤可能なエリアを再検討すると、より多くの企業の選考を受けられるようになります。
こうした調整をキャリアアドバイザーと相談しながら進めることで、自分に合った求人が見つかりやすくなります。
段階的にキャリアアップする戦略を立てる/最初は条件を緩めてスタート→スキルUPして理想の働き方を目指す
希望条件に合う求人が見つからない場合、まずは条件を少し緩めてスタートし、スキルアップをしながら理想の働き方を目指すという戦略もあります。
例えば、最初は希望年収より少し低めの求人に就き、経験を積みながら年収アップを狙う方法があります。
また、短時間勤務や契約社員から始めて、正社員登用や昇進を目指すことも可能です。
転職活動は一度きりではなく、キャリアを積み重ねていくものなので、最初の一歩として現実的な選択をすることが重要です。
手帳未取得・障がい区分で断られたとき(障がい者手帳がない、精神障がいや発達障がいで手帳取得が難航している、支援区分が違うなど)の対処法について
dodaチャレンジの障がい者雇用枠の求人は、基本的に障がい者手帳を持っていることが条件となっています。
そのため、手帳を取得していない場合や、取得の手続きが進んでいない場合は、別の方法を検討する必要があります。
主治医や自治体に手帳申請を相談する/ 精神障がい・発達障がいも条件が合えば取得できる
精神障がいや発達障がいのある人の中には、手帳を取得できることを知らなかったり、手続きが面倒に感じて申請をしていない人もいます。
しかし、手帳があることで応募できる求人の幅が広がるため、まずは主治医や自治体の福祉窓口に相談し、取得の可能性を確認することが重要です。
特に、精神障がい者保健福祉手帳は、診断書の内容や病歴によって取得できることがあります。
医師と相談しながら手続きの進め方を決めるのがよいでしょう。
就労移行支援やハローワークで「手帳なしOK求人」を探す/一般枠での就職活動や、就労移行後にdodaチャレンジに戻る
手帳を取得しないまま転職活動を進めたい場合は、一般枠での就職活動を検討するのも一つの方法です。
ハローワークや就労移行支援では、手帳がなくても応募できる求人を紹介してくれることがあります。
また、就労移行支援を利用して実績を積み、その後手帳を取得してからdodaチャレンジに再登録する方法もあります。
就労移行支援では、ビジネスマナーやPCスキルのトレーニングを受けながら、安定した職場への就職を目指すことができます。
医師と相談して、体調管理や治療を優先する/手帳取得後に再度登録・相談する
障がい者雇用枠での転職活動が難しい場合、まず体調管理や治療を優先し、安定した状態になってから手帳を取得し、再度転職活動を進めるのも一つの方法です。
手帳の取得には一定の診断期間や手続きが必要ですが、取得後は障がい者枠の求人に応募しやすくなるため、長期的に見て転職の選択肢を増やすことができます。
焦らずに自分のペースで準備を進めることが大切です。
その他の対処法/dodaチャレンジ以外のサービスを利用する
dodaチャレンジで求人を紹介してもらえなかった場合でも、他の転職サービスや支援機関を活用することで、新たなチャンスを見つけることができます。
例えば、障がい者向け転職エージェント(atGP、サーナ、アットジーピーなど)を活用すると、より多くの求人を紹介してもらえる可能性があります。
また、ハローワークや地域の就労支援機関に相談することで、地元の求人情報を得ることができるかもしれません。
複数の転職サービスを併用しながら、自分に合った働き方を探していくことが大切です。
dodaチャレンジで断られた!?発達障害や精神障害だと紹介は難しいのかについて解説します
dodaチャレンジは障がい者向けの転職支援サービスとして多くの求職者をサポートしています。
しかし、精神障害や発達障害を持つ方の中には「dodaチャレンジで求人を紹介されなかった」「面談後に断られてしまった」という声もあります。
これは、企業側の受け入れ態勢や、障がいの特性によって求人数が限られてしまうことが関係しています。
本記事では、身体障害・精神障害・発達障害を持つ方の就職事情について詳しく解説し、dodaチャレンジでの紹介が難しい場合の対処法についても紹介します。
身体障害者手帳の人の就職事情について
身体障害者手帳を持つ方は、比較的就職しやすい傾向にあります。
これは、身体的な障がいは企業側が「どのような配慮をすればよいか」が明確なためです。
一方で、障がいの程度や種類によっては、選べる職種が限られることもあります。
障害の等級が低い場合は就職がしやすい
身体障害者手帳を持つ方の中でも、比較的軽度(等級3級~6級程度)の場合、就職はしやすい傾向にあります。
特に、視覚や聴覚に軽度の障がいがある場合や、片手・片足の不自由さ程度であれば、事務職やIT系の職種での採用が期待できます。
企業側も、バリアフリーの環境を整えやすく、配慮がしやすいことから、採用を積極的に進めるケースが多いです。
身体障がいのある人は、障がいの内容が「見えやすい」ことから、企業側も配慮しやすく採用しやすい傾向にある
身体障がいは、外見や診断書の情報から企業が状況を把握しやすく、どのような配慮が必要かが明確になりやすいのが特徴です。
そのため、企業側も安心して採用を進めやすい傾向があります。
例えば、車いすを使用している場合は、バリアフリーの環境を整えるだけで働けるため、企業側も受け入れやすいです。
また、聴覚障がいがある場合には、筆談やチャットツールの活用によって問題なく業務を遂行できるケースも多いです。
企業側が合理的配慮を明確にしやすい(例:バリアフリー化、業務制限など)から、企業も安心して採用できる
企業が障がい者を採用する際には、合理的配慮を提供する必要があります。
身体障がいの場合、配慮すべき点が明確であり、例えばオフィスのバリアフリー化、特定の業務を制限するなどの対応をすれば、問題なく働ける場合が多いです。
一方で、精神障がいや発達障がいは、見た目では判断しづらく、どのような配慮が必要なのかが企業側にとって分かりにくいことがあります。
この点が、就職の難しさにつながることもあります。
上肢・下肢の障がいで通勤・作業に制約があると求人が限られる
通勤や作業に制約がある場合、在宅勤務が可能な求人や、特定の業務に特化したポジションを探す必要があります。
特に、製造業や営業職など、身体を動かす仕事では採用が難しくなるため、デスクワーク中心の職種を選ぶことが重要です。
コミュニケーションに問題がない場合は一般職種への採用も多い
身体障がいがあっても、コミュニケーションに問題がなければ、一般職種への採用のチャンスが広がります。
特に、電話対応や対面での接客が求められない事務職や、IT系の仕事では、障がいの影響が少ないため、採用の可能性が高まります。
PC業務・事務職は特に求人が多い
身体障がいのある方の中でも、特に事務職やPC業務の求人は多くあります。
データ入力、経理、総務などの仕事は、障がいの影響を受けにくく、企業側も採用しやすい職種の一つです。
精神障害者保健福祉手帳の人の就職事情について
精神障害者保健福祉手帳を持つ方の就職は、身体障がい者とは異なる課題があります。
精神障がいは外見からは分かりにくく、症状の波があるため、企業側が受け入れに慎重になるケースが多いです。
また、合理的配慮が必要な場合でも、企業側がどのように対応すればよいか分からず、採用を控えることもあります。
そのため、精神障がい者の方がdodaチャレンジで求人を紹介してもらえないと感じることがあるのです。
精神障がいは「症状の波」があるため、企業側が採用を慎重に検討する
精神障がいの特性として、調子が良いときと悪いときの差が大きいことがあります。
そのため、企業側が「どのように業務を調整すればよいのか」「どの程度の負担を軽減すればよいのか」が分かりにくく、採用を慎重に進める傾向があります。
配慮が難しいと判断されると、求人紹介が難しくなる
企業側が合理的配慮を提供しづらいと判断した場合、求人紹介の数が限られることがあります。
特に、対人コミュニケーションが必要な仕事や、ストレス耐性が求められる職種では、精神障がい者の採用が難しくなるケースが多いです。
定着率が低いと見られることがある
精神障がいのある方は、職場の環境によっては継続勤務が難しくなることがあります。
そのため、企業側が「長く働いてもらえるかどうか」を気にする傾向があり、採用を慎重に判断することがあります。
症状の安定性や職場での継続勤務のしやすさが重視される
精神障害や発達障害のある方が就職する際、企業側は「安定的に働けるかどうか」を特に重視します。
これは、業務を長く続けられるかどうかが採用の大きなポイントになるためです。
例えば、うつ病や双極性障害の場合、体調の波が大きく、継続的な勤務が難しいケースもあります。
そのため、企業は「長期間、安定して働けるか」を慎重に判断します。
応募する際には、自分の体調管理の方法や、ストレス対策をしっかり伝えることが重要です。
また、医師と相談しながら、職場での配慮が必要なポイントを整理し、アドバイザーや企業に具体的に伝える準備をしておくとよいでしょう。
見えにくい障がいなので、企業が「採用後の対応」に不安を持ちやすいのが現実
精神障害や発達障害は、外見からは分かりにくいため、企業側が「どのような対応をすればよいのか分からない」と感じることがあります。
例えば、業務の指示を一度で理解するのが難しい場合や、特定の環境では集中力が続かない場合など、仕事に影響が出る要素があると、企業側が慎重になりやすいです。
このため、採用担当者が具体的な配慮事項を把握しやすいように、事前に「自分がどのような環境なら力を発揮できるのか」「どのような配慮があればスムーズに働けるのか」を伝えることが重要です。
面接時に、実際の業務に支障がないことを説明できれば、企業側の不安を軽減し、採用の可能性を高めることができます。
採用面接での配慮事項の伝え方がとても大切!
精神障害や発達障害を持つ方の採用面接では、自分に合った働き方や必要な配慮を適切に伝えることが成功の鍵となります。
例えば、「1回の指示では理解が難しいので、要点をメモする時間をもらえると助かる」「視覚情報が整理されている環境のほうが集中しやすい」など、具体的な配慮事項を伝えることで、企業側も受け入れやすくなります。
また、「どのような配慮があれば、自分の能力を最大限に発揮できるか」を説明できるように準備しておくことも大切です。
例えば、「集中力を保つために定期的に短い休憩を取りたい」「ストレスを感じやすい業務は事前に相談したい」など、自分にとって必要なサポートを具体的に伝えることで、採用の可能性を高めることができます。
療育手帳(知的障害者手帳)の人の就職事情について
知的障害を持つ方が就職する際には、療育手帳の区分(A判定・B判定)が影響することが多いです。
一般就労を目指すか、福祉的就労(就労継続支援A型・B型)を活用するかは、手帳の判定や本人の能力、職場環境によって異なります。
療育手帳の区分(A判定 or B判定)によって、就労の選択肢が変わる
療育手帳は、知的障害の程度によってA判定(重度)とB判定(中軽度)に分かれています。
この区分によって、一般就労の可能性や、受けられる支援が異なります。
A判定(重度)の場合、一般就労は難しく、福祉的就労(就労継続支援B型)が中心
A判定(重度)の方は、一般企業での就労が難しい場合が多く、就労継続支援B型(福祉的就労)を利用するケースが一般的です。
B型事業所では、比較的簡単な作業を行いながら、働くためのスキルや生活リズムを整えることができます。
ただし、一部のA判定の方でも、特定の分野で得意なスキルがあれば、一般企業への就職が可能な場合もあります。
例えば、単純作業を繰り返す仕事や、特定の作業を集中して行う仕事では、強みを活かせる可能性があります。
B判定(中軽度)の場合、一般就労も視野に入りやすい
B判定(中軽度)の場合は、一般企業での就労が比較的可能であり、障がい者雇用枠を利用して働く人も多いです。
特に、事務補助や軽作業、データ入力などの職種では、知的障害があっても十分に働ける環境が整っている企業が増えています。
B判定の方が一般就労を目指す場合は、ハローワークの障がい者窓口や、就労移行支援事業所を活用することで、適切なサポートを受けながら転職活動を進めることができます。
障害の種類と就職難易度について
障がいの種類によって、就職の難易度が異なります。
一般的に、身体障がいは企業側の合理的配慮がしやすく、就職しやすい傾向にあります。
一方で、精神障がいや発達障がいの場合、企業がどのように配慮すればよいか分からないことが多く、就職が難しくなることがあります。
知的障害の場合は、判定の区分によって就労の選択肢が変わり、A判定の方は福祉的就労が中心、B判定の方は一般就労の可能性が高くなります。
それぞれの障がいの特性を理解し、自分に合った働き方を見つけることが大切です。
転職活動の際には、就労移行支援やキャリアアドバイザーを活用し、自分の強みを活かせる職場を探すとよいでしょう。
| 手帳の種類 | 就職のしやすさ | 就職しやすい職種 | 難易度のポイント |
| 身体障害者手帳(軽度〜中度) | ★★★★★★ | 一般事務・IT系・経理・カスタマーサポート | 配慮事項が明確で採用企業が多い |
| 身体障害者手帳(重度) | ★★ | 軽作業・在宅勤務 | 通勤や作業負担によって求人が限定 |
| 精神障害者保健福祉手帳 | ★★ | 事務補助・データ入力・清掃・在宅ワーク | 症状安定と継続勤務が評価されやすい |
| 療育手帳(B判定) | ★★★★ | 軽作業・事務補助・福祉施設内作業 | 指導・サポート体制が整った環境で定着しやすい |
| 療育手帳(A判定) | ★★ | 福祉的就労(A型・B型) | 一般就労は難しく、福祉就労が中心になる場合が多い |
障害者雇用枠と一般雇用枠の違いについて
障がい者の方が就職を目指す際、選択肢として「障害者雇用枠」と「一般雇用枠」のどちらで応募するかを考える必要があります。
それぞれの雇用枠には異なる特徴があり、自分の希望する働き方や職場環境によって適した選択肢が変わります。
障害者雇用枠は、企業が障害者雇用促進法に基づいて設けているもので、障がいのある方が安心して働けるように配慮された環境が整っていることが多いです。
一方で、一般雇用枠は障がいの有無に関係なく、すべての応募者が同じ基準で採用選考を受ける枠組みとなります。
それぞれの特徴を詳しく見ていきましょう。
障害者雇用枠の特徴1・企業が法律に基づき設定している雇用枠
障害者雇用枠は、企業が法的な義務として設けている枠組みであり、障がいのある方が安定して働けるように環境が整えられていることが特徴です。
企業側は、障がい者が働きやすいように合理的配慮を行うことが求められます。
例えば、勤務時間の調整や、職場のバリアフリー化、業務内容の工夫などが挙げられます。
障害者雇用枠の特徴2・障害者雇用促進法により、民間企業は従業員の2.5%以上(2024年4月〜引き上げ)を障がい者として雇用するルールがある
障害者雇用促進法により、民間企業は一定の割合で障がい者を雇用する義務があります。
2024年4月からは、この法定雇用率が2.5%に引き上げられ、大企業だけでなく中小企業にも障がい者雇用の取り組みが求められるようになっています。
このルールに基づき、多くの企業が障害者雇用枠を設けており、専用の求人を公開しています。
これにより、障がい者の方は一定の枠組みの中で働くことができ、企業側も障がいに対する理解を深めながら雇用を進めることができます。
障害者雇用枠の特徴3・障害をオープンにし配慮事項を明確に伝えた上で雇用される
障害者雇用枠では、採用時に障がいの内容を企業に伝える必要があります。
これは「オープン就労」とも呼ばれ、企業側が障がいの特性を理解した上で、適切な配慮を行いながら働ける環境を提供するためです。
例えば、通院のための勤務時間調整や、業務内容の調整、必要な設備の導入など、障がい者が働きやすいように企業がサポートを行います。
そのため、自分の障がい特性や配慮が必要な点を事前に整理し、面接時にしっかり伝えることが重要です。
一般雇用枠の特徴1・障害の有無を問わず、すべての応募者が同じ土俵で競う採用枠
一般雇用枠では、障がいの有無に関係なく、すべての応募者が同じ基準で選考を受けます。
そのため、職務能力や経験、スキルが重視され、障がいに対する特別な配慮は基本的にありません。
この枠で採用される場合、企業は障がいを理由に特別な待遇を用意するわけではなく、一般の社員と同じ条件で働くことになります。
そのため、職場の環境が自分に合っているかどうか、慎重に見極める必要があります。
一般雇用枠の特徴2・障害を開示するかは本人の自由(オープン就労 or クローズ就労)
一般雇用枠で応募する場合、障がいを企業に開示するかどうかは本人の判断に委ねられます。
障がいを開示して就職する場合は「オープン就労」、開示せずに働く場合は「クローズ就労」と呼ばれます。
オープン就労を選ぶと、職場での配慮を受けられる可能性が高くなりますが、障害者雇用枠と比べると、企業側が必ずしも配慮を約束するわけではありません。
一方で、クローズ就労を選ぶと、選考の際に障がいが影響しないメリットがありますが、配慮を受けられないため、働きやすさに影響することがあります。
一般雇用枠の特徴3・基本的に配慮や特別な措置はないのが前提
一般雇用枠で採用された場合、企業側は基本的に障がいに対する特別な配慮を行う義務はありません。
そのため、職場環境や業務内容が自分に合っているかを慎重に確認することが大切です。
ただし、企業によっては柔軟な対応を行ってくれる場合もあり、配慮が必要な場合は入社後に相談することで、ある程度の対応を受けられるケースもあります。
そのため、一般雇用枠での就職を考える場合は、事前に企業の社風や働き方についてリサーチすることが重要です。
年代別の障害者雇用率について/年代によって採用の難しさは違うのか
障がい者雇用率は、年代によって異なる傾向があります。
一般的に、若年層(20代)の方が採用されやすく、高齢になるほど就職が難しくなる傾向があります。
障害者雇用状況報告(2023年版)を元に紹介します
厚生労働省が発表した「障害者雇用状況報告(2023年版)」によると、企業の障がい者雇用率は年々上昇しているものの、40代以降の求職者の採用は難しくなる傾向にあります。
これは、企業が若年層を採用することで、長期間の雇用を見据えやすいという理由が背景にあります。
20代や30代の障がい者求職者は、ポテンシャル採用の機会も多く、未経験でもチャレンジしやすい環境が整っています。
一方で、40代以降は即戦力としてのスキルや経験が求められることが多く、就職活動に時間がかかることがあります。
そのため、年代に応じた戦略を立てながら、求人を探すことが重要です。
| 年代 | 割合(障害者全体の構成比) | 主な就業状況 |
| 20代 | 約20~25% | 初めての就職 or 転職が中心。
未経験OKの求人も多い |
| 30代 | 約25~30% | 安定就労を目指す転職が多い。
経験者採用が増える |
| 40代 | 約20~25% | 職歴次第で幅が広がるが、未経験は厳しめ |
| 50代 | 約10~15% | 雇用枠は減るが、特定業務や経験者枠で採用あり |
| 60代 | 約5% | 嘱託・再雇用・短時間勤務が中心 |
若年層(20〜30代)の雇用率は高く、求人数も多い
20〜30代の障がい者求職者は、比較的採用されやすい傾向があります。
これは、企業が若手の育成に力を入れていることや、長期的に働いてもらえる可能性が高いと判断するためです。
特に、IT・事務・営業などの職種では、未経験でもポテンシャル採用を行う企業が多く、新しいスキルを身につけながら成長できる環境が整っています。
若年層は転職市場でも需要が高く、積極的に求人を探すことで、自分に合った職場を見つけやすいです。
また、20〜30代の求職者は、就労移行支援などのサポートを利用することで、就職のチャンスをさらに広げることができます。
職業訓練やスキルアップの機会を活用しながら、希望する職種での採用を目指すとよいでしょう。
40代以降は「スキル・経験」がないと厳しくなる
40代以降の障がい者求職者は、スキルや職務経験が求められる傾向が強くなります。
企業は即戦力としての活躍を期待するため、過去の業務経験や専門的なスキルがないと、採用が難しくなる場合があります。
特に、未経験の分野に挑戦しようとすると、企業側が「若年層の方が育成しやすい」と判断し、40代以上の求職者が不利になりやすいです。
そのため、40代以降の方は、自分の強みや経験を活かせる職種を選ぶことが重要です。
また、キャリアチェンジを希望する場合は、資格取得や職業訓練を受けることで、新しい分野への転職の可能性を高めることができます。
障がい者向けの専門エージェントやハローワークを活用し、自分に合った職場を見つける工夫が必要です。
50代以上は「短時間勤務」「特定業務」などに限られることが多い
50代以上の求職者は、フルタイムの正社員採用が難しくなる傾向があります。
企業は若年層や40代の求職者を優先するケースが多いため、50代以上の方が働ける求人は「短時間勤務」や「特定の業務に限定されたポジション」が中心となります。
例えば、事務補助、清掃、軽作業、データ入力など、比較的負担の少ない業務が多く、週3〜4日勤務や時短勤務の求人が主流です。
また、シニア向けの再雇用制度を活用する方法もあります。
50代以上の求職者は、自分の体調や生活スタイルに合わせて、無理のない範囲で働ける職場を選ぶことが大切です。
就労支援機関や自治体のサポートを活用しながら、自分に合った働き方を模索するとよいでしょう。
dodaチャレンジなどの就活エージェントのサービスに年齢制限はある?
就職支援エージェントの多くは、明確な年齢制限を設けていませんが、実際の利用者の多くは「20〜50代前半」に集中しています。
dodaチャレンジなどの障がい者向けエージェントも、基本的には幅広い年齢層に対応していますが、企業の採用ターゲットの傾向として、50代以上の求職者の紹介は限られることが多いです。
年齢制限はないが 実質的には「50代前半まで」がメインターゲット層
dodaチャレンジでは、公式には年齢制限は設けていません。
しかし、企業が求める人材の傾向を考えると、実際に求人紹介を受けられるのは50代前半までの方が多いです。
特に、即戦力としてのスキルや経験を求められることが多いため、50代以降の求職者は「過去の職歴を活かせる仕事」を探すことが重要になります。
また、シニア向けの求人は少ないため、エージェントだけに頼らず、他の就職支援サービスも併用するとよいでしょう。
ハローワーク障がい者窓口や障がい者職業センター(独立行政法人)も併用するとよい
50代以上の求職者は、dodaチャレンジだけでなく、ハローワークの障がい者窓口や障がい者職業センターなどの公的支援機関を併用すると、より多くの求人情報を得ることができます。
ハローワークでは、障がい者向けの専門相談員が対応し、個別のキャリアカウンセリングや職業訓練の案内をしてくれます。
また、障がい者職業センターでは、障がいに配慮した職場実習や、職業訓練の機会を提供しており、再就職を目指す際に有効なサポートを受けることができます。
また、シニア向けの就職支援サービスや、地方自治体のシニア向け求人支援も活用すると、より幅広い選択肢を得ることができます。
年齢に関係なく、自分のスキルや経験を活かせる職場を見つけるために、さまざまな支援サービスを活用するとよいでしょう。
dodaチャレンジで断られたときの対処法について|よくある質問と回答
dodaチャレンジで求人に応募したものの、断られてしまうことは誰にでも起こり得ることです。
しかし、断られたことをそのまま悲観せず、次に繋げるためにどう対処するかが大切です。
まず、断られた理由をしっかりと確認し、そのフィードバックを次回の応募や面接に活かすことが重要です。
例えば、応募書類の内容が不足していたり、企業の求めるスキルや経験に合致していなかった場合など、改善点を把握することができます。
面接で断られた場合、再度自分の強みを見直し、次回に向けた準備を行うことが成功に繋がります。
また、dodaチャレンジにはさまざまな求人があるため、他の求人にも積極的に挑戦することが有効です。
断られたことを一つの学びとし、前向きに次のステップに進むことが、最終的に自分にぴったりな仕事を見つけるための鍵となります。
dodaチャレンジの口コミや評判について教えてください
dodaチャレンジは、障がい者向けの就職支援サービスとして高い評価を得ています。
特に、スタッフの丁寧な対応や、利用者に寄り添ったサポートが口コミで好評です。
求人の紹介が個々のニーズに合わせて行われるため、利用者からは自分に合った職場を見つけやすいと感じる人が多いようです。
また、面接対策や就職後のフォローも行われており、利用者が安心して就職活動を進められる環境が整っています。
関連ページ:dodaチャレンジの口コミは?障害者雇用の特徴・メリット・デメリット
dodaチャレンジの求人で断られてしまったらどうすれば良いですか?
dodaチャレンジで求人を断られてしまった場合は、まずその理由を確認することが重要です。
理由によっては、改善点を見つけて次に活かすことができます。
例えば、応募書類の内容が不十分だった場合や、応募資格に合致していなかった場合などです。
面接で断られた場合は、フィードバックを求めることで、次回の面接に活かせるポイントを得ることができます。
また、他の求人に再挑戦することも大切です。
関連ページ:dodaチャレンジで断られた!?断られた理由と対処法/難しいと感じた体験談
dodaチャレンジで面談後に連絡なしの理由について教えてください
dodaチャレンジで面談後に連絡がない場合、いくつかの理由が考えられます。
まず、求人先が面接を続けるかどうかを決定するまでに時間がかかる場合があります。
また、面接後に他の候補者と比較している可能性もあります。
その場合は、担当者に確認を取ることが有効です。
連絡が遅れる理由としては、手続きの進行や求人側の都合などもありますので、冷静に待つことが重要です。
関連ページ:dodaチャレンジから連絡なしの理由と対処法/面談・求人・内定それぞれのケースと連絡なしの理由
dodaチャレンジの面談の流れや聞かれることなどについて教えてください
dodaチャレンジの面談は、まず利用者の状況を理解することから始まります。
最初に、自分の障がいや希望する職場環境について詳しく話すことが求められます。
その後、具体的な求人情報や応募条件について説明があり、適切な求人を見つけるためのアドバイスが行われます。
面談では、自己紹介や過去の職歴についても質問されることが一般的です。
自分の強みや希望する仕事に関して、しっかり伝えることが大切です。
関連ページ:dodaチャレンジの面談から内定までの流れは?面談までの準備や注意点・対策について
dodaチャレンジとはどのようなサービスですか?特徴について詳しく教えてください
dodaチャレンジは、障がいを持つ方々の就職支援サービスで、個々の状況に合わせた就職支援を行っています。
特徴的なのは、障がい者向けの特別な支援を提供するだけでなく、求人の紹介から面接対策、就職後のフォローまで、幅広いサービスが提供されている点です。
専任のカウンセラーが丁寧にサポートし、働きやすい環境の職場を見つけるための手助けをしてくれるため、安心して利用できるサービスです。
障がい者手帳を持っていないのですが、dodaチャレンジのサービスは利用できますか?
dodaチャレンジのサービスは、障がい者手帳を持っていない方でも利用することができます。
障がいがあると感じている方や、就職活動に困難を感じている方に対しても、適切なサポートが提供されます。
手帳を持っていない場合でも、障がいに配慮した職場探しをサポートしており、個別の状況に応じたアドバイスを受けることができるため、安心して利用できます。
dodaチャレンジに登録できない障害はありますか?
dodaチャレンジは、広範囲の障がいに対応していますが、特に重度な障がいがある場合や、就労に支障をきたす場合は、サービスの提供が難しいことがあります。
具体的には、就業が困難な状況にある方などです。
しかし、ほとんどの障がいには対応しており、個別に相談を受け付けているため、まずは自分の状況を相談することが重要です。
dodaチャレンジの退会(登録解除)方法について教えてください
dodaチャレンジの退会手続きは簡単で、公式ウェブサイトまたはサポートセンターを通じて行うことができます。
退会を希望する場合、サポートセンターに連絡し、手続きを進めることで、スムーズに登録解除が完了します。
万が一、再度利用したくなった場合でも、再登録が可能なので、気軽に退会できます。
dodaチャレンジのキャリアカウンセリングはどこで受けられますか?
dodaチャレンジのキャリアカウンセリングは、オンラインでも受けることができます。
自宅にいながら、専任のキャリアアドバイザーと相談できるため、便利で効率的です。
また、全国にある支援センターでも対面でのカウンセリングを受けることができ、直接会って相談したい方にも対応しています。
利用者のライフスタイルに合わせたカウンセリングの方法が提供されています。
dodaチャレンジの登録には年齢制限がありますか?
dodaチャレンジには年齢制限はありません。
障がいを持つ方であれば、年齢に関係なく利用することができます。
どの年代の方でも、自分に合った職場を見つけるためのサポートが受けられるため、幅広い世代の方々がサービスを利用しています。
年齢や経験に関わらず、就職活動をサポートしてくれるので、安心して利用できます。
離職中ですがdodaチャレンジのサービスを利用できますか?
離職中の方でも、dodaチャレンジのサービスは利用可能です。
離職後の就職活動を支援するサービスであり、キャリアカウンセリングや求人の紹介など、再就職に向けた手厚いサポートを提供しています。
離職中であっても、次の職場に向けて適切なサポートを受けながら、安心して就職活動を進めることができます。
学生ですがdodaチャレンジのサービスを利用できますか?
dodaチャレンジは、学生でも利用することができます。
特に、就職活動を始めたばかりの学生にとっては、障がいに配慮した企業情報や面接対策など、就職活動を支援してくれるサービスです。
学生のうちから自分に合った職場を見つけるためのアドバイスやサポートが受けられるため、卒業後の就職活動に向けて安心して準備を進めることができます。
参照:よくある質問(dodaチャレンジ)
dodaチャレンジは断られない?その他の障がい者就職サービスとの比較一覧
dodaチャレンジは、障がい者雇用を専門に扱う転職エージェントとして、多くの求職者に利用されています。
キャリアアドバイザーが求職者のスキルや適性を見極めたうえで、最適な求人を紹介してくれるため、通常の求人サイトと比べて選考通過率が高い点が特徴です。
応募後に断られるリスクを減らすために、履歴書や職務経歴書の添削、面接対策、企業との条件交渉など、さまざまなサポートを提供しています。
そのため、初めての転職活動でも安心して進められると評判です。
他の障がい者就職サービスと比較すると、dodaチャレンジはエージェント型のため、求職者の希望や特性に応じた求人紹介が可能で、断られるリスクが少ない点がメリットです。
LITALICOワークスやウェルビーのような就労移行支援サービスとは異なり、即戦力となる人材を対象とした求人が中心であり、転職活動に集中したサポートを受けることができます。
障がい者雇用に理解のある企業の求人が多数あるため、安心して利用できるサービスとして支持されています。
| 就職サービス名 | 求人数 | 対応地域 | 対応障害 |
| dodaチャレンジ | 1,500 | 全国 | 全ての障害 |
| アットジーピー(atGP) | 1,500 | 全国 | 全ての障害 |
| マイナビパートナーズ紹介 | 350 | 全国 | 全ての障害 |
| LITALICOワークス | 4,400 | 全国 | 全ての障害 |
| 就労移行支援・ミラトレ | 非公開 | 全国 | 全ての障害 |
| ランスタッドチャレンジ | 260 | 東京、神奈川、千葉、埼玉、大阪 | 全ての障害 |
| Neuro Dive | 非公開 | 全国 | 全ての障害 |
| Cocorport | 非公開 | 首都圏、関西、東海、福岡 | 全ての障害 |
dodaチャレンジで断られた!?断られた理由や対処法|難しいと感じた詳しい体験談まとめ
dodaチャレンジで応募した企業から断られる場合、その理由はさまざまです。
応募先の企業が求めるスキルや経験に不足があったり、選考のタイミングが合わなかったりするケースが一般的です。
特に障がい者雇用枠では、企業が求める働き方やスキルセットが独自の基準に基づいているため、求職者の適性が企業側の条件と一致しないことがあります。
また、応募書類や面接でのアピールポイントが不十分だった場合も、選考が進まず断られることがあるのです。
対策としては、キャリアアドバイザーのサポートを積極的に活用することが重要です。
履歴書や職務経歴書の内容を見直し、企業が求めるスキルや経験に合ったアピールポイントを強調しましょう。
さらに、応募する企業の業界情報や選考基準を事前にリサーチし、面接の際に自分の強みを効果的に伝えられるよう準備することが大切です。
dodaチャレンジは、キャリアアドバイザーからのフィードバックを活かすことで、断られる確率を減らし、より良い企業とのマッチングを目指せるサービスといえるでしょう。