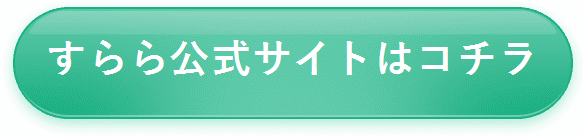すららは不登校でも出席扱いになる?なぜ?出席扱いになる理由について
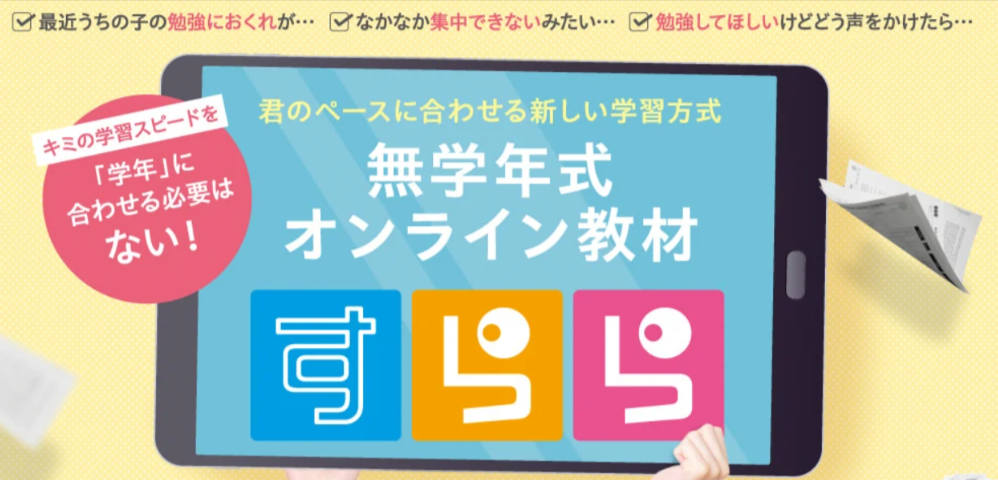
不登校の子どもにとって、「自宅での学習が学校の出席扱いになるかどうか」はとても大きな関心事です。
保護者としても、「学習が進んでいないのでは」「将来の進学に不利では」といった不安を抱えがちですが、実は文部科学省のガイドラインにより、一定条件を満たせば家庭学習でも出席扱いが可能です。
すららは、この条件にしっかり対応しており、すでに多くの自治体や学校で「出席扱い」として認定されている実績もあります。
では、なぜすららなら出席扱いにできるのか?その理由について、5つの柱でわかりやすく解説していきます。
理由1・学習の質と記録の証明がしっかりしている
すららが出席扱いとして認められる大きな理由の一つが、学習内容の「見える化」と「記録性」です。
学習した内容や進捗、問題への正答率、取り組んだ時間などがすべてシステム上に保存され、レポート形式で出力することができます。
これは、学校へ提出する客観的な「学習の証拠」として使えるため、担任や校長先生からの信頼にもつながります。
保護者がわざわざ記録をつけなくても、すららのシステムがすべて自動で記録・管理してくれるので手間も少なく、継続もしやすいのが特長です。
学校側に「客観的な学習記録レポート」を提出できる
すららでは、子どもが何の教材をどれだけやったのか、正解率はどうだったのかなど、学習の過程を自動で蓄積・保存しています。
この情報は、PDFなどの形式で出力でき、学校に提出することで「しっかりと学習している証拠」になります。
学校側も判断しやすく、出席扱いの判断材料として非常に有効です。
保護者の手間なく、自動的に学習状況が可視化される/これが学校側からも「安心材料」として評価されやすい
保護者が一つひとつ記録をつけたり、学校に提出する書類をまとめる負担が軽減されるのも大きなポイントです。
システムが自動で学習履歴を管理してくれるため、学習の可視化が非常にスムーズに行えます。
この透明性が、学校側からも「信用できる教材」として評価される理由の一つになっています。
理由2・個別最適な学習計画と継続支援がある
不登校の子どもにとって、自分のペースで取り組める環境はとても大切です。
すららでは、専任の「すららコーチ」が一人ひとりの学力や性格、生活スタイルに合わせて学習計画を作成してくれます。
子どもが無理なく取り組めるよう配慮されたスモールステップの設計や、声かけのタイミングなど、継続的なサポート体制が整っているのが魅力です。
こうした個別支援によって、学びが「一過性のもの」ではなく「積み重ねられるもの」になる点も、出席扱いとして評価される大きな理由です。
すららはコーチがいることで、学習の「計画性」と「継続性」をセットでアピールできる
すららの専任コーチは、ただ学習内容を提示するだけでなく、「どのように進めるか」「いつやるか」といった学習習慣づくりまでサポートします。
計画性を持って学べる環境が整っているという点は、学校側にも大きな説得力を持ちます。
すららは、専任コーチが継続的にサポートし、学習計画を作成してくれる
コーチは定期的に学習の進み具合をチェックし、「少し無理があるな」「もう少し進めそうだな」といった個別の状況に応じたアドバイスをくれます。
そのため、子ども自身も自信を持って学び続けることができます。
すららは、無学年式で学習の遅れや進み具合に柔軟に対応してくれる
学年に縛られず、理解に合わせてどこまでも戻れる無学年式カリキュラムも、不登校の子どもにぴったり。
学校の授業スピードについていけない子でも、自分のペースで確実にステップアップしていけます。
理由3・家庭・学校・すらら三者で連携ができる
出席扱いを受けるためには、家庭・学校・教材提供者の三者が連携することが不可欠です。
すららでは、出席扱いを希望するご家庭に対して「どう申請すればいいか」「必要な書類はなにか」といった情報をしっかり提供してくれます。
また、フォーマットが整った学習レポートの作成や提出タイミングのアドバイスも行ってくれるため、学校側とも円滑に連携をとることができます。
先生と保護者の間に“すらら”という信頼できる媒介があることで、申請がスムーズに通る可能性がぐっと高まります。
すららは、必要書類の準備方法の案内をしてくれる
はじめて出席扱いを申請する場合、「何を出せばいいの?」「いつ出すの?」と戸惑う保護者も多いはず。
すららでは、そういった疑問に対して丁寧に案内をしてくれる体制が整っているため、安心して準備ができます。
すららは、専任コーチが学習レポート(フォーマットの用意)の提出フォローしてくれる
すららでは、出席扱い申請に必要な「学習レポート」の作成を、専任コーチが丁寧にフォローしてくれます。
たとえば、学習記録の提出が必要な場合には、フォーマットを用意してもらえるだけでなく、「いつまでに」「どのような形で」学校へ出せばよいかもアドバイスしてくれるのが特長です。
保護者自身がゼロから書類を用意するのではなく、コーチが状況をヒアリングしながら進めてくれるため、はじめての申請でも安心して取り組めます。
すららは、担任・校長と連絡をとりやすくするためのサポートをしてくれる
不登校の子どもに関することとなると、学校とのやりとりに対して保護者がストレスを感じるケースも少なくありません。
すららでは、そうした親の不安を軽減するために、学校とのコミュニケーションをスムーズに進める工夫もされています。
たとえば、担任や校長へ渡す説明資料や学習計画書のテンプレートを用意してくれたり、必要に応じてコーチが代わりに内容をまとめてくれたりといったサポートがあります。
これにより、出席扱いの申請も円滑に進められるようになります。
理由4・文部科学省が認めた「不登校対応教材」としての実績
すららは、文部科学省の定める「出席扱い要件」を満たす学習教材として、全国の教育現場で導入実績のある信頼性の高いツールです。
これまでにも多数の子どもたちが、すららを通じて家庭で学習し、その内容が学校での「出席扱い」として認められてきました。
この実績があるからこそ、学校側も安心して「すららでの学習」を学習活動として受け入れやすいのです。
また、自治体の教育委員会と連携し、支援対象として推奨されているケースもあるため、教材としての信頼性が非常に高いと言えます。
すららは、全国の教育委員会・学校との連携実績がある
すららは、特定の学校だけでなく、全国の多くの教育委員会・小中学校で実際に導入・活用された実績を持ちます。
不登校支援としての活用例も豊富で、各地域における成功事例が積み重なっているため、学校側もすららを出席扱いの学習手段として受け入れやすい傾向があります。
すららは、公式に「不登校支援教材」として利用されている
文部科学省のガイドラインにも対応しているすららは、公式に「不登校支援教材」として明記された教材のひとつです。
家庭学習での活用はもちろん、教育委員会との連携や報告書提出のサポートもあるため、制度面においても安心して利用できます。
出席扱いを目指す家庭には、心強い味方となるでしょう。
理由5・学習環境が「学校に準ずる」と認められやすい
出席扱いになるかどうかは、家庭での学習が「学校に準ずる教育内容かどうか」が判断基準のひとつになります。
すららは、小中学校の学習指導要領に準拠しており、国語・算数・理科・社会・英語といった主要教科をしっかりカバーしています。
さらに、進捗状況や正答率のデータが残るため、学習の成果を可視化できる点も大きなポイントです。
学びの質と評価がシステムで管理されていることが、学校側から「準ずる学習環境」として認定されやすい要因となっています。
すららは、学習内容が学校の学習指導要領に沿っている
すららのカリキュラムは、文部科学省の学習指導要領をベースに作られており、学校で学ぶ内容をしっかりカバーしています。
授業と同等の内容を学べるため、出席扱いの判断材料として非常に有利になります。
すららは、学習の評価とフィードバックがシステムとしてある
テストや小問に対する正答率、理解度の推移などがすべてデータ化され、視覚的に把握できます。
コーチによるコメントもつくため、単なる“こなした”ではなく“理解したかどうか”を明確に示すことができ、学校にも伝えやすい構成です。
すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いの制度の申請方法の流れ紹介
不登校でも「出席扱い」が認められる制度があることをご存じでしょうか?文部科学省の通達によって、家庭での学習が学校教育に準じる内容であり、学校長が認めた場合には、在宅学習を「出席」としてカウントできる仕組みがあります。
家庭用タブレット教材「すらら」は、この制度に沿って学習できる仕組みとサポート体制が整っており、多くの不登校の子どもたちがこの制度を活用しています。
ここでは、すららを使って出席扱いを申請するための流れを、4つのステップに分けてわかりやすく解説します。
申請方法1・担任・学校に相談する
まず最初に行うべきは、通っている学校の担任または校長先生への相談です。
「出席扱い制度」を活用したいという意向を伝え、どのような手順が必要か、何を準備すればいいかを学校側に確認しましょう。
出席扱いの認定は学校長の判断によるため、早めに相談を始めることが大切です。
また、学習の方法や進捗報告の形式についても、事前に話し合っておくことで申請がスムーズに進みます。
すらら側で用意されている学習レポートや申請フォーマットが役立つので、それも合わせて学校に提示しましょう。
出席扱いの申請に必要な書類・条件を確認する
出席扱いを受けるためには、いくつかの条件と必要書類があります。
主に求められるのは、学習内容の記録(レポート)、学校長への申請書、場合によっては医師の診断書などです。
学校によって細かい提出内容が異なることもあるため、必ず事前に学校側と詳細を確認しておきましょう。
すららは、この手続きのためのレポート出力や記入例も提供してくれるので、安心して準備を進められます。
申請方法2・医師の診断書・意見書を用意(必要な場合のみ)する
出席扱いの申請において、必ずしも診断書が必要なわけではありませんが、不登校の理由によっては医師の意見が求められることもあります。
たとえば、精神的な理由で学校に通えない場合、専門医による診断があると学校側の判断がスムーズになります。
診断書の取得は任意ではあるものの、出席扱いの説得力を高める材料の一つとして有効です。
不登校の理由によっては、診断書が求められるケースもある
学校によっては、「不登校の理由が医師の判断で明確であること」を出席扱いの条件としているケースもあります。
特に、精神的な不調や発達障害などが背景にある場合、専門医からの診断書や意見書が求められることが多いため、あらかじめ準備しておくと安心です。
精神科・心療内科・小児科で「不登校の状態」と「学習継続が望ましい旨」を書いてもらう
診断書に記載してもらう内容としては、「現在学校に通うことが困難な状態であること」と、「家庭学習などを通じて学習の継続が望ましいこと」の2点が大切です。
すららを使って学んでいる旨を伝えることで、医師側も状況を理解しやすく、協力的に書類を用意してくれるケースが多いです。
申請方法3・すららの学習記録を学校に提出する
すららでは、日々の学習状況(学習時間・進捗・正答率など)を自動で記録し、必要に応じて学習レポートとしてダウンロードできます。
このレポートを学校に提出することで、「家庭でもしっかり学習している」という証拠となり、出席扱いの条件を満たす後押しになります。
保護者が記録をつける必要がないため、手間も少なく、学校からの信頼も得やすいのが大きな特長です。
学習進捗レポートをダウンロードし担任または校長先生に提出
すららのマイページから、学習記録をPDF形式などで簡単に出力できるため、印刷して学校に提出すればOKです。
教科別・日付別の学習履歴が整理されているため、担任や校長先生にも非常に伝わりやすく、信頼性の高い資料として評価されやすいのがポイントです。
出席扱い申請書を学校で作成(保護者がサポート)
最終的な申請書の作成は学校側が行いますが、内容のベースとなる学習履歴や医師の意見書は保護者が用意します。
担任と相談しながら、すららのレポートと合わせて提出することで、申請書に説得力が加わります。
提出後、学校長の承認をもって正式に「出席扱い」となります。
申請方法4・学校・教育委員会の承認
出席扱い制度の最終的な判断は、校長先生または教育委員会によって下されます。
すららのように教育的根拠のある教材を使用していれば、多くのケースで「学びの継続」が評価され、出席扱いが認められやすくなります。
必要に応じて、学校と教育委員会が連携し、保護者に説明がある場合もあるため、柔軟に対応できるよう準備しておきましょう。
学校長の承認で「出席扱い」が決まる
最終的に出席扱いとなるかどうかは、校長先生の判断に委ねられます。
提出した学習記録や医師の意見、学習計画の妥当性などを総合的に判断して、「出席」と認定されるかが決まります。
すららはこうした要件を満たす構成になっているため、申請成功の可能性が高い教材といえます。
教育委員会に申請が必要な場合は、学校側と連携して行う
自治体によっては、教育委員会への提出が必要になるケースもあります。
この場合は学校が主体となって申請を進めるため、保護者は学校との連携を保ち、必要書類の補完を丁寧に行うことが大切です。
すららのサポート体制を活用しながら、安心して申請手続きを進めていきましょう。
すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いを認めてもらうメリットについて解説
不登校という選択をしたあと、多くのご家庭が気にするのが「このままでは内申点に響くのでは?」「進学の選択肢が狭まるのでは?」という不安です。
しかし、すららを使って家庭学習を続けることで、文部科学省が定めた出席扱いの制度を活用することができます。
これは単に“欠席”が“出席”に変わるというだけではなく、子どもの未来や親の心の余裕にも大きな影響を与えてくれます。
ここでは、出席扱いが認められることによって得られる3つの大きなメリットをご紹介します。
メリット1・内申点が下がりにくくなる
学校に行けない日が続くと、多くの親御さんが最も気にするのが「内申点」への影響です。
日本の進学システムでは、出席日数は内申点に大きく関係しており、長期の欠席が続くと「学力とは関係なく評価が下がる」という現実があります。
しかし、すららを使った家庭学習を出席扱いにできれば、日数をカウントできるため、こうした心配がぐっと減ります。
学校での実際の出席が難しくても、すららでの取り組みが評価の対象となることで、進学の選択肢も広がる可能性が高まります。
出席日数が稼げることで、内申点の評価も悪化しにくい
中学・高校の内申点では「出席日数」も加味されるため、すららを通じて出席扱いになれば、成績とは別に“欠席が多い”という理由で評価が下がるのを防げます。
これは定期テストや授業態度で評価を補えない場合にも、大きな助けとなります。
中学・高校進学の選択肢が広がる
内申点が確保できれば、推薦入試や面接を含む入試方式にもチャレンジしやすくなります。
将来的に「学校に戻る」「通信制を選ぶ」など、どの道を選んだとしても、出席扱いにしておくことは確実にプラスです。
メリット2・「遅れている」「取り戻せない」という不安が減る
不登校になると、子ども自身が「もう勉強についていけないのでは」「学校の友だちより遅れている」と焦りを感じることがあります。
この“学習の遅れ”への不安が自己肯定感を下げ、さらに学習意欲を奪ってしまう悪循環に陥ることも。
ですが、すららは無学年式の教材で、自分のペースで戻って学習ができるため、「わからないところ」を確実に理解しながら進めることができます。
継続的に学ぶ環境があることで、こうした不安を大きく減らすことができ、子どもにとっての安心感にもつながります。
すららで継続的に学習することで、授業の遅れを気にしなくていい
授業についていけるか不安なまま復学するよりも、すららで基礎から着実に学習しておくことで「理解できてる」「進んでいる」という安心感が得られます。
無理に合わせなくていいことが、自信につながります。
学習環境が整うことで子どもの自己肯定感が低下しにくい
「勉強していない自分はダメだ」と思ってしまいがちな子でも、すららで成果が見えると「自分はやれてる」と思えるようになります。
これは、不登校の状態において非常に大きな心の支えとなります。
メリット3・親の心の負担が減る
子どもが学校に行けないことで、親御さんも「どうすればいいのか分からない」「誰にも相談できない」といった孤独感や不安を抱えることが少なくありません。
すららを導入することで、専任コーチが子どもの学習状況を一緒に見守ってくれますし、出席扱いに必要な手続きもサポートしてくれます。
学校との連携に不安がある場合でも、すらら側がサポートしてくれることで「親が全部抱え込まなくていい」という状態を作ることができ、精神的な負担が大きく軽減されます。
学校・家庭・すららコーチで協力体制ができる/1人で不安を抱える必要がない
「誰にも相談できない」「自分だけが悩んでいる」と感じてしまう親御さんにとって、すららコーチの存在は大きな救いになります。
学校とのやり取りにも付き添ってくれるような感覚で寄り添ってくれるので、「一緒に支えてくれる人がいる」と思えることが、心の余裕にもつながります。
不登校のお子さんが「すらら」を使って出席扱いを得るためには、正しい手順と必要な条件を満たすことがとても重要です。
制度として認められているとはいえ、すべてのケースで自動的に出席扱いになるわけではありません。
学校側の理解、学習の記録、必要な書類など、いくつかの注意点を押さえておくことで、スムーズに申請を進めることができます。
ここでは、出席扱いを確実に認めてもらうために知っておきたい3つの重要なポイントについて、わかりやすく解説します。
注意点1・学校側の理解と協力が必須
出席扱いは、文部科学省が定めたガイドラインに基づいた制度ですが、最終的に判断を下すのは「学校長(校長先生)」です。
そのため、どれだけ家庭で学習していても、学校側がその事実や制度を理解してくれなければ、出席扱いにはなりません。
まずは担任の先生に丁寧に相談し、すららが文科省の指針に沿った教材であることを説明しましょう。
可能であれば、教頭先生や校長先生にも早い段階で話を通しておくと、後の流れがスムーズになります。
「すららは文科省ガイドラインに基づく教材」ということを丁寧に説明する必要がある
すららは、文部科学省の出席扱いガイドラインに準拠した教材であり、学習内容や記録機能、サポート体制などが公式に認められた仕様になっています。
この点を学校にしっかり伝えることで、「すららを使っている=信頼できる学習環境である」と理解してもらいやすくなります。
必要に応じて、すららの資料を一緒に持参する/担任だけではなく教頭や校長にも早めに相談する
学校に説明する際には、すららの公式サイトからダウンロードできるパンフレットや説明資料を持参するのがおすすめです。
特に校長先生との面談では、「教材の信頼性」や「実績」を数字や実例で示すことで、前向きに検討してもらいやすくなります。
注意点2・医師の診断書や意見書が必要な場合がある
すべてのケースで必要ではありませんが、不登校の原因が体調不良や精神的な不安、発達障害などに関連している場合は、医師の診断書または意見書の提出を求められることがあります。
これは「学校に通えないことが客観的に確認できる状態であるか」を判断するための基準となります。
診断書があることで、学校側もより安心して出席扱いを認めやすくなりますので、必要に応じて早めに準備しておきましょう。
不登校の原因が「体調不良」や「精神的な理由」の場合は医師の診断書・意見書が必要になることが多い
たとえば、適応障害、うつ症状、ASDやADHDなど、何らかの診断がある場合は、医師による文書が求められる傾向があります。
診断書には「現在の状態」や「家庭学習が望ましいとされる理由」などを含めてもらえるよう依頼しましょう。
通っている小児科や心療内科で「出席扱いのための診断書が欲しい」と伝える
医師への相談時には、単に「診断書ください」ではなく、「出席扱い制度の申請に必要」と具体的に伝えるのがコツです。
すでにすららで学習していることや、家庭での様子をメモして持参すると、よりスムーズに書いてもらえます。
医師に「家庭学習の状況」や「意欲」を具体的に説明して、前向きな記載をお願いする
たとえば「毎日30分はタブレット学習に取り組んでいる」「コーチからのフィードバックも受けている」など、学習の具体的な様子を医師に説明することで、「家庭学習によって成長が見込める」といった前向きな記載をお願いしやすくなります。
注意点3・学習時間・内容が「学校に準ずる水準」であること
出席扱いとして認められるには、「学習している」というだけでは不十分です。
学校の授業と同等、もしくはそれに準じた学習内容と時間が確保されている必要があります。
すららは、学習指導要領に準拠したカリキュラムで、国・数・理・社・英など主要教科をしっかりカバーしています。
さらに、学習履歴が自動で記録されるため、学校に「どの程度、どの教科を、どれだけ学んでいるか」を明確に示せます。
出席扱いの条件を満たすには、こうした“学習の質”を重視することが重要です。
出席扱いにするためには、「単なる自習」ではNG/「学校の授業に準じた学習内容」である必要がある
家庭での読書やノートまとめなどの“自習”では、出席扱いは難しいとされています。
その点、すららは教科書レベルの講義動画・確認テスト・問題演習を備えた「学習プログラム型」の教材なので、教育的効果が高く評価されやすいです。
学校にも納得してもらいやすいのが強みです。
学習時間は、学校の授業時間に近い形を意識(目安:1日2〜3時間程度)する
出席扱いに認定されるためには、「家庭での学習時間が学校に準ずる」ことも条件となる場合があります。
文部科学省のガイドラインでも、学習時間の目安について明確な時間設定はありませんが、学校の授業時間に近づけることが推奨されています。
小中学生であれば、1日2〜3時間を目安に、定期的に継続して学習していることが望ましいとされています。
無理をする必要はありませんが、「毎日短時間でも取り組む姿勢」が大切です。
すららなら1単元15〜20分のスモールステップで進められるため、日々の積み上げがしやすい教材です。
全教科をバランスよく進める(主要教科だけだとNGな場合もある)
出席扱いが認められるためには、「学校で学ぶ教科に準じた学習」が求められることがあります。
たとえば国語・算数(数学)・英語だけではなく、理科・社会などを含めた全教科に取り組んでいるかどうかもチェックされるポイントのひとつです。
すららは最大5教科に対応しており、教科ごとに学習の進捗が管理できるので、バランスよく進めやすいのが強みです。
申請時には、どの教科をどのくらい学習しているかを示すレポートを準備しておくと、説得力がぐんと増します。
注意点4・学校との定期的なコミュニケーションが必要
出席扱いの制度は、「一度申請したら終わり」というものではなく、継続的な学習の様子を学校と共有し続けることが前提になります。
つまり、「その後もきちんと学習しているかどうか」を学校が把握できる仕組みが必要なのです。
すららでは、学習記録のレポートが自動で保存されるため、それを月に1回提出するだけでも十分な報告になります。
学校側との信頼関係を保ち続けることで、次回以降の申請もスムーズになり、継続的に出席扱いを受けやすくなります。
出席扱いにするためには、「学校と家庭で学習状況を共有」することが条件になることが多い
学習の記録や成果を学校と共有することが、出席扱いの申請における大前提です。
どんなに家庭で頑張っていても、それを学校側が把握できなければ出席として認定することはできません。
定期的な報告が重要です。
月に1回は学習レポートを提出(すららでダウンロードできる)すると良い
すららの保護者用マイページからは、学習記録をPDF形式で簡単にダウンロードできます。
このレポートを月に1度程度、担任または教頭先生に提出することで、学習の進捗をきちんと共有できます。
忙しい学校側にも好印象を与えられます。
学校から求められた場合は、家庭訪問や面談にも対応する
出席扱いの判断には、家庭の学習環境や保護者の意向も確認されることがあります。
そのため学校側から家庭訪問や面談の申し出があった場合には、できるだけ柔軟に対応することが望ましいです。
誠実な対応が信頼関係につながります。
担任の先生とは、こまめにメールや電話で進捗共有をすると良い
直接会って話せる機会が少なくても、メールや電話で定期的にお子さんの様子を伝えるだけでも効果は大きいです。
「どの教科をどこまで進めた」「今日はやる気が出なかったけど少しでもやった」など、ちょっとした情報の共有が信頼の鍵になります。
注意点5・教育委員会への申請が必要な場合もある
地域によっては、出席扱いを最終決定するのが学校長だけでなく、「教育委員会の承認」が必要になるケースもあります。
このような場合には、学校と家庭の連携に加え、必要な書類をそろえて提出しなければなりません。
申請書の書式や必要な添付書類(診断書や学習レポート)については、事前に学校と相談しながら準備を進めるのがベストです。
すららのフォーマットを活用し、見やすく整った形で提出することが通過のポイントとなります。
教育委員会向けの資料準備も、学校と相談しながら進める
教育委員会への申請が必要な場合、保護者だけで準備を進めるのは難しいこともあります。
そのため、まずは担任や校長先生と相談し、「何をどこまで用意するか」を明確にしておくことが重要です。
すららのレポートや医師の意見書など、必要に応じて資料をそろえて提出する準備を整えておきましょう。
すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いを認めてもらうための成功ポイントを解説
すららを活用して出席扱いを得たいと考えるご家庭にとって、申請がスムーズに通るかどうかは非常に重要なポイントです。
条件を満たしていても、学校側の理解や協力が得られなければ思うように進まないこともあります。
そんなときこそ、準備や伝え方ひとつで結果が大きく変わってくるものです。
ここでは、すららを活用して出席扱いの承認を得るために押さえておきたい“成功のコツ”をご紹介します。
前例の提示、本人の意欲、現実的な学習計画の立て方、そしてすららコーチの活用など、すぐに実践できる具体策をお伝えしていきます。
ポイント1・学校に「前例」をアピールする
学校側が出席扱いに対して慎重になる理由のひとつが、「うちの学校では前例がない」という不安です。
これに対して効果的なのが、すららの他校での活用実績を紹介すること。
すららは、全国の多くの学校・教育委員会で出席扱いの教材として採用されており、その事例を共有することで学校側にも安心してもらえるケースが多いです。
公式サイトや資料にある導入実績や活用事例を印刷し、面談の際に見せながら話をすると説得力が増します。
「すららで出席扱いになった他の学校」の事例を学校に紹介すると効果的
たとえば、「○○県の○○中学校では、すららを使って家庭学習を行い、正式に出席扱いとなった」などの事例を共有することで、学校の不安を和らげることができます。
実際の声やアンケート結果などもあると、なお効果的です。
すららの公式サイトに実績紹介があるので、それをプリントして持参する
すららの公式ページには、教育委員会や学校との連携実績が紹介されています。
それらをプリントアウトして担任や校長先生に見せることで、「全国でも認められている教材である」という安心感を与えられます。
ポイント2・「本人のやる気」をアピール
出席扱いが認められるかどうかは、「家庭学習の継続性」だけでなく「本人の学習意欲」も大きく関係しています。
学校側が心配するのは、「親が無理やりやらせているだけでは?」という点。
その不安を払拭するためには、本人の意思ややる気を直接伝える工夫が効果的です。
自分の言葉で書いた目標や、実際に頑張っている姿を見せることで、学校側も「この子は学ぶ意志がある」と前向きに受け止めてくれるようになります。
本人が書いた学習の感想や目標を提出すると良い
簡単なメモや日記形式で、「今日は国語を頑張った」「将来は○○になりたいから英語を勉強中」など、本人の言葉で学習への姿勢を伝えると、学校側の印象が大きく変わります。
実際に書かせて提出するだけでも効果は抜群です。
面談がある場合は、本人も参加して「頑張っている」と伝えると良い
可能であれば、学校との面談に本人も同席させ、「すららで勉強を続けている」「また学校に戻れるように頑張っている」と直接言葉にして伝えるのがおすすめです。
無理のない範囲で、本人の存在を見せることが大切です。
ポイント3・「無理なく、継続可能な学習計画」を立てる
出席扱いを認めてもらったあとに最も重要なのは、「継続すること」です。
最初に勢いで頑張っても、1ヵ月後にはストップしてしまっては意味がありません。
そのため、申請時点から「現実的で続けられる計画」を立てておくことが成功の鍵となります。
すららでは、子どもの学習傾向や得意・不得意を把握したうえで、専任のコーチが学習スケジュールの相談に乗ってくれるため、無理なく進めることが可能です。
継続が最重要だから、本人に合わせた計画が必須となる
子どもによって集中力や学習に取り組める時間帯は違います。
「朝しか集中できない」「週末はできるけど平日は無理」など、本人の性格や生活スタイルに合わせた計画にすることで、無理なく継続できる環境が整います。
すららコーチに相談して、現実的なスケジュールを一緒に立ててもらう
すららの強みは、専任コーチの存在。
希望すればコーチがヒアリングの上でスケジュール提案をしてくれるため、家庭で全部を考える必要はありません。
プロの視点から、負担の少ない継続学習の土台を作ってくれます。
ポイント4・「すららコーチ」をフル活用する
すららのコーチは、ただの学習サポーターではありません。
出席扱いを得るための重要な「学習記録の出力」や「レポートの整備」なども、コーチのサポートによってスムーズに行えます。
保護者が一人で悩むことなく、必要な書類や手続きの流れもコーチと相談しながら進められるので、不安を大きく減らすことができます。
学習計画の立案、進捗管理、モチベーション維持にいたるまで、多角的に支えてくれる存在です。
出席扱いのために必要なレポート作成や学習証明はコーチがサポートしてくれる
すららの学習レポートは、出席扱い申請の際に非常に重要な資料となります。
どのデータをどのように出力するか、どこをアピールすべきかといった実務的な部分も、すららコーチが丁寧にサポートしてくれるため、初めてでも安心です。
すららは不登校でも出席扱いになる?実際に利用したユーザーや子供の口コミ・評判を紹介します
すららは、不登校のお子さんでも条件を満たせば学校で「出席扱い」として認められる可能性がある教材です。
文部科学省はオンライン学習を出席扱いにできる指針を出しており、学校長の判断で承認されれば、すららを使った学習も出席日数に含められる場合があります。そのため、長期欠席で悩む家庭にとっては心強い選択肢です。
実際の口コミでは「家にいながら安心して勉強できた」「学校に行けなくても学習が遅れず助かった」という声が多く聞かれます。一方で「学校によって対応が違うので、担任や校長先生と相談する必要があった」という意見もあります。
すららを不登校支援として利用する際は、学習状況を記録したり提出できるようにしておくと安心です。口コミを見る限り、学習習慣の維持や自信回復に役立ったと評価する声が多く、不登校の子どもにとって大きな支えとなっています。
良い口コミ1・うちの子は中2から不登校になり、内申点が心配でした。でも、すららで学習を続けたことで「出席扱い」にしてもらえました
良い口コミ2・ 学校に行けなくなってから勉強が完全に止まってたけど、すららを始めて「毎日ちょっとずつやればいい」と思えた。時間も自分で決められるし、誰にも急かされないからストレスがない
良い口コミ3・ 不登校になってから、家で何もせずにゲームばかり。イライラして何度も怒ってしまっていましたが、すららを導入してから、1日10分でも学習に取り組むようになって、家庭の雰囲気がかなり良くなりました
良い口コミ4・ 小学校の時から算数が苦手で、それが原因で不登校になったけど、すららはアニメで説明してくれるし、ゆっくり復習できたので、だんだん分かるようになった
良い口コミ5・すららを始めて半年経った頃、子どもが「学校の授業も分かりそう」と言い出しました。完全に無理だと思ってた登校が、部分登校からスタートできました
悪い口コミ1・ 低学年だと、すららを一人で操作するのが難しくて、結局親がつきっきり。タブレットを使った勉強というより、「親子で一緒にやるドリル」みたいになってしまいました
悪い口コミ2・最初は頑張ってたけど、やっぱり「一人でやる」ことに飽きてしまいました。キャラが励ましてくれるのも、最初は嬉しかったけど、そのうち「うざい」と感じてしまった
悪い口コミ3・すららで学習は続けていたものの、学校が「出席扱い」を認めてくれませんでした。教育委員会にも相談しましたが、地域によって判断が違うのが辛かった
悪い口コミ4・続ければ続けるほど料金が積み上がっていくので、経済的にきつくなってきました。他のオンライン教材よりは高めの印象。
悪い口コミ5・勉強にブランクがあったので仕方ないけど、「すららをやってすぐに成績が上がる!」ってわけではなかったです
【すらら】は不登校でも出席扱いになる?についてのよくある質問と回答
すららを利用しているご家庭からは「不登校の子どもが家庭で学習していることは出席扱いになるの?」という質問が多く寄せられます。
結論から言うと、条件を満たせば出席扱いになる場合があります。文部科学省のガイドラインでは、ICT教材を活用して家庭で学習している場合、学校と連携して適切に学習状況が確認できれば出席として認められることがあるのです。
ただし、これは全国一律ではなく、学校や教育委員会の判断によって対応が異なります。そのため「必ず出席扱いになる」とは限らない点に注意が必要です。口コミでも「出席扱いにしてもらえた」という声と「学校によって認めてもらえなかった」という声の両方がありました。
利用を検討する際には、事前に学校へ相談し、すららでの学習がどのように評価されるのか確認しておくことが大切です。出席扱いの有無に関わらず、自宅で安心して学習を継続できる点はすららの大きな強みと言えるでしょう。
すららはうざいという口コミがあるのはどうしてでしょうか?
すららに対して「うざい」といったネガティブな口コミが見られる理由には、主に「続けるのが難しい」「料金が高いと感じた」「サポートが合わなかった」などの個人的な体験が影響しています。
とはいえ、実際には多くの利用者が「自分のペースで進められて助かる」「子どもが前向きに取り組めている」と高く評価していることも事実です。
学習スタイルが人によって異なるため、合う・合わないの感想は分かれる傾向があります。
気になる方は無料体験や資料請求で実際の内容を確認してみると安心です。
関連ページ:【すらら】はうざい!?小中高の料金や最悪の噂は?タブレット教材の口コミを比較
すららの発達障害コースの料金プランについて教えてください
すららには「発達障害専用コース」という明確な区分はありませんが、ADHDやASD、LDなどの子どもに対応しやすい「ユニバーサルデザイン」の教材構成と、個別サポート体制が整っています。
料金プランは一般の家庭用と同じで、障害の有無によって割引や免除があるわけではありませんが、質の高いサポートを全員が等しく受けられる設計です。
また、すららコーチが特性に応じた学習計画を提案してくれるため、個別最適な支援を受けられる点が大きな魅力です。
関連ページ:すららは発達障害の料金が安くなる?学習障害や慮育手帳を持っている人の料金は?
すららのタブレット学習は不登校の子供でも出席扱いになりますか?
はい、すららは文部科学省の出席扱い要件を満たす教材として、多くの自治体・学校で「出席扱い」として認められています。
出席扱いとなるためには、家庭と学校が連携し、学習記録や進捗状況を学校側に報告・共有する必要があります。
すららでは、学習時間・内容・正答率などがレポートとして自動生成されるため、申請に必要な証拠を簡単に準備できます。
不登校でも自宅でしっかり学んでいることを示す手段として非常に有効です。
関連ページ:すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いの申請手順・注意点・成功のポイントについて
すららのキャンペーンコードの使い方について教えてください
すららのキャンペーンコードは、入会時に専用フォームの「キャンペーンコード欄」に入力することで適用されます。
期間限定で「入会金無料」や「教材費割引」などのお得な特典が用意されていることがあり、事前に公式サイトや提携サイトで配布中のコードをチェックしておくのがおすすめです。
キャンペーン内容は時期によって変わるため、最新の情報を確認したうえで申し込むようにしましょう。
入力ミスや使用期限切れに注意が必要です。
関連ページ:すららのキャンペーンコードの入手方法は?入会無料の特典について
すららの退会方法について教えてください
すららの退会は「解約」と「退会」で手続き内容が異なります。
「解約」は月額料金の支払いを止めることで、「退会」は会員情報自体を削除するステップです。
解約は電話でのみ受け付けており、登録者の名前・ID・連絡先などを確認後、希望日に解約を行う流れになります。
退会も電話で可能ですが、解約後に再開の可能性を考えて情報を残しておくご家庭も多いです。
すららコールに連絡すれば、丁寧に案内してくれるので安心して手続きできます。
関連ページ:すららの退会手続き・方法について解説します/解約・休会はいつまでにする?
すららは入会金と毎月の受講料以外に料金はかかりますか?
基本的に、すららは入会金と月額受講料以外に、教材費や機器代などの追加料金はかかりません。
タブレットは自前の端末を使用する仕組みのため、別途教材セットなどを購入する必要もなく、費用が明瞭です。
ただし、インターネット環境は必要ですので、通信費は各自の契約内容によります。
教材の更新費や年間一括請求などの隠れた費用もなく、シンプルな料金体系で安心して利用できます。
1人の受講料を支払えば兄弟で一緒に使うことはできますか?
すららでは、基本的に受講者1人ごとに個別のIDが発行され、学習履歴や進捗が管理される仕組みになっています。
そのため、1人分の受講料で兄弟複数人が一緒に利用することはできません。
ただし、兄弟で同時に申し込む場合、兄弟割引が適用されることがあります。
詳細は申込前に確認するとよいでしょう。
それぞれが自分専用のアカウントで学習できることで、AI分析やサポートも精度が保たれます。
すららの小学生コースには英語はありますか?
はい、すららの小学生コースにも英語の学習コンテンツが含まれています。
英語は聞く・話す・読む・書くの4技能をバランスよく学べるよう構成されており、アニメーションや音声付きで楽しみながら学べる工夫がされています。
英語に初めて触れるお子さんでも無理なくスタートできる構成なので、「英語が苦手」というイメージを持たせにくいのが特長です。
文法や単語の反復練習も含まれており、基礎からしっかり学べます。
すららのコーチからはどのようなサポートが受けられますか?
すららには「すららコーチ」と呼ばれる専門スタッフがつき、学習の進め方や計画の立て方について個別にサポートしてくれます。
とくに不登校や発達障害のあるお子さんに対しては、特性に合わせた学習スケジュールを提案したり、つまずきやすい単元をフォローしたりと、きめ細かい対応が可能です。
また、保護者へのサポートも行っており、学習相談や不安の相談にも対応してくれる心強い存在です。
参照:よくある質問(すらら公式サイト)
【すらら】は不登校でも出席扱いになる?他の家庭用タブレット教材との違いを比較しました
不登校のお子さまを持つご家庭にとって、「自宅学習で出席扱いになるかどうか」は非常に大きなポイントですよね。
最近では多くの家庭用タブレット教材が登場していますが、実際に出席扱いが認められる教材は限られています。
この記事では、すららの出席扱い制度の特徴を中心に、他社の人気教材とどう違うのかを比較してみました。
学校との連携のしやすさ、学習記録の提出方法、レポート機能など、気になる点をわかりやすく解説しています。
出席扱いを目指して家庭学習を始めたい方は、ぜひ参考にしてくださいね。
| サービス名 | 月額料金 | 対応年齢 | 対応科目 | 専用タブレット |
| スタディサプリ小学講座 | 2,178円~ | 年少~6年生 | 国語、算数、理科、社会 | ✖ |
| RISU算数 | 2,680円~ | 年中~6年生 | 算数 | 必須 |
| スマイルゼミ小学生コース | 3,278円~ | 小学1年~6年 | 国語、算数、理科、社会、英語 | 必須 |
| すらら | 8,800円~ | 1年~高校3年 | 国語、算数、理科、社会、英語 | ✖ |
| オンライン家庭教師東大先生 | 24,800円~ | 小学生~浪人生 | 国語、算数、理科、社会、英語 | ✖ |
| トウコベ | 20,000円~ | 小学生~浪人生 | 国語、算数、理科、社会、英語 | ✖ |
| 天神 | 10,000円~ | 0歳~中学3年 | 国語、算数、理科、社会、音楽、図画工作 | 必須 |
| デキタス小学生コース | 3,960円~ | 小学1年~6年 | 国語、算数、理科、社会 | ✖ |
| DOJO学習塾 | 25,960円~ | 小学生~中学生 | 漢字・語い・英単語・計算 | 必須 |
| LOGIQ LABO(ロジックラボ) | 3,980円~ | 小学1年~6年 | 算数、理科 | ✖ |
| ヨミサマ。
|
16,280円~ | 小学4年~高校生 | 国語 | ✖ |
| 家庭教師のサクシード | 12,000円~ | 小学生~高校生 | 国語、算数、理科、社会 | ✖ |
| ヨンデミー | 2,980円~ | なし | 読書 | ✖ |
すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いの制度・注意点・申請手順まとめ
「すららを使えば出席扱いになるって聞いたけど、本当に?」「出席扱いってどうやって申請するの?」という疑問をお持ちの保護者の方に向けて、この記事では出席扱い制度の基本から申請の流れ、注意すべき点まで丁寧にまとめました。
すららは文部科学省のガイドラインに沿って作られた教材なので、全国の多くの学校で出席扱いとして活用されています。
でも、学校ごとに対応の差があるため、申請する際のポイントを押さえておくことがとても重要。
この記事を読めば、学校とのやりとりもスムーズに進みますよ。